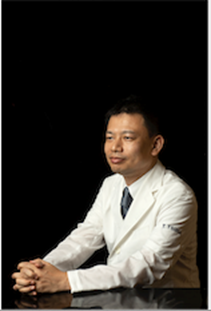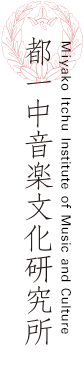「西洋医学を突き詰めると、東洋医学の背中が見えてくる」
NTT東日本関東病院 リウマチ膠原病科 部長 津田篤太郎さん
津田篤太郎さんはNTT東日本関東病院のリウマチ膠原病科部長として、西洋医学と東洋医学両方の知見を元に診療を行なっています。都一中に就いて三味線の研鑽にも励む津田さんは、「日本独自の医学と音楽は、同じような道をたどっている」といいます。
一中 お稽古のときに、津田先生は西洋医学のお医者さまでありながら漢方医の資格もおありと聞きました。
津田 漢方専門医ですね。日本東洋医学会という学会があって、漢方専門医という資格を出しているんです。鍼灸もこの頃勉強し始めました。
一中 日本の医療水準が江戸時代には世界最高だったというお話と日本の音楽と医学が歴史的に同じ道を辿っているお話が興味深かったです。明治時代になると、漢方医は医師免許が取れなかったんですね。今は先生のように漢方を研究している方は少ないんですか。
津田 数少ないです。
一中 それがね、日本の音楽の歴史とおんなじなんですよ。
津田 ぴったりおんなじですね。
一中 先生は膠原病(こうげんびょう)がご専門ですが、治りにくい病気ですよね。
津田 そうなんですが、この10年20年で薬がガラッと変わってしまって。免疫学がすごく進歩して使える薬が増えたので、従来は直せなかったのが今は上手に直せる、ということも増えてきました。これは西洋医学の薬の話ですが、西洋医学をどんどん突き詰めていくと、東洋医学の背中が見えてくるみたいな話があっておもしろいですね。
一中 日本が西洋音楽の影響を受ける前の音楽を聞いてもらうということで、ドイツの現代音楽祭に呼ばれたことがあります。そこで一中節そのままをやったんです。現代音楽の最先端では、一中節が大事にしている空白とか静寂、拍節リズムがないことを追求しだしています。指揮者が振り始めても、空白があってから音が出始めることって、日本は何百年も前からやっている。それが現代音楽の最先端、そういうこととおんなじですね。
津田 この間お稽古のときに微分音(びぶんおん)のお話をされて、微分音というのは20世紀もだいぶ後ろの方に出てくる話なのに、江戸時代にあったということでしたね。
一中 当然のこととしてね。
津田 西洋音楽で出てくるのは電子音楽になってからですもんね。電気的に周波数を調律できるようになって初めて西洋音楽の文脈に出てくるんですけど、江戸時代は普通に演奏していた。何も使わずにですね。西洋音楽も西洋医学も突き詰めると昔の日本の人たちの背中が見えてくる。おもしろいですね。今は薬が増えすぎて、すごい数になってきているんですよ。人間の遺伝子が読めるようになって、次から次へ病気の遺伝子を発見しまして、それに対してお薬を作るようになってきた。そうするとすごいお薬の種類になってきて。
一中 それは西洋医学の薬ですか。原料は何なんですか。
津田 最先端は微生物に作らせたり、培養細胞に作らせたりした薬ですね。シャーレの中でネズミの腎臓の細胞を増やして、その中に遺伝子を入れ込むと、それを細胞たちが読んでどんどんお薬を作ってくれる。
一中 漢方薬は自然の原料からできていて、西洋の薬は石油からできているというイメージがあります。
津田 石油など有機化合物から作られているお薬は、現代医学にとって非常に大事なんです。そういう化学的なやり方で合成されるお薬は、もはやちょっと古い世代の、20世紀後半のお薬みたいな感じですね。21世紀のこの20年ほどは、生き物つまり、ウイルス、細菌、培養細胞とかそういうものにお薬を作らせているんですね。
一中 今のコロナのワクチンも。
津田 まさにそうですね。
一中 コロナのワクチン以外にもそういう作り方はあるんですか。
津田 実は、遺伝子が体の中に入ってくるというのは日常茶飯事で、絶えず起きています。いろんなウイルスを介して外来の遺伝子が体の中に、細胞の中に入ってくる。よそからの遺伝子をどんどん細胞に植えつけていますし、人間の細胞の中の遺伝子は太古の昔からそういう侵入を受け続けているので、細胞の中には遺伝子の状態で眠っているウイルスというのがいるんですよね。それがあるとき目を覚まして細胞の外へファッと出てきたりする。そういう遺伝子の行き来というのは、みなさんが思っている以上に非常に頻繁に起きています。だいたい、毎日の食事なんかでもおなじことが起こっています。食べ物を食べるでしょ。それは外のものですよね。それがお腹の中に入って、栄養になって、自分の一部になる。そのうち垢とかになって外に出ていく。外のものは絶えず中に入ってきて、外に出て行っているんで、3ヶ月ほどしたら自分の体の細胞はまったく入れ替わっているわけですよね。物質として「私」が存在しているんじゃなくて、構造の同一性として「私」が存続しているんです。新しいものにどんどん入れ替わり、セルフ・リニューアルしていく「私」というのは、ちょうど伊勢神宮の式年遷宮のようなものです。
江戸時代の日本の医学は水準が高かった
一中 江戸時代の医学が世界最高水準だったというのは、どういうことですか。中国の漢方と日本にあった医学は違うんでしょうか。
津田 まず、その中国というのがすごいところで、砂漠もあるし湿原もあるし川もあるし山もあるし平原もあって、寒い地方から南の暖かい地方までバラエティに富んだ土地があって、植物とか鉱物とかものすごくたくさんあるんですね。そのたくさんある中から、お薬として使えるものも非常にたくさん取れたわけです。それをもとに医学が発展してきた。それに比べてヨーロッパは、 暮らしやすい土地だったと思いますがあまり気候の変化がなくて、植物の種類が非常に少なかった。ギリシャの方だけちょっと多かった。それで古代ギリシャには薬物学書があった。ヨーロッパは長いこと医学がそんなに発展しなかったんです。病気の治療の手段が非常に少なかった。こんなに西洋医学と言われだしたのは、19世紀に入ってからです。化学的合成法の発展によっていろんな化合物を作り出せるようになり、お薬を工業的に大量生産することもできるようになった。
一中 昔はお医者さんがドイツ語でカルテを書いていました。
津田 ドイツは化学が盛んでした。西洋医学の歴史はたかだか200年とか、多く見積もっても300年とかです。
一中 それは西洋音楽の歴史と同じですね。
津田 そうなんです。
一中 ギリシャでは、整った音、つまり整数比の音の比率を順番に聞かせると人間の体が整う。つまり、音を医療として使おうとピタゴラスが考えた。
津田 その背景に「四体液説」というのがあって、四つの体液のバランスによって健康が保たれているというヒポクラテスとかの学説があって、その学説を支えたのがまさにギリシャの植生が多様で薬用となる植物がたくさん取れるということでした。古代ギリシアの医学と中国の医学は相当似ています。四つの要素というのが、血液と水と黄色い胆汁と黒い胆汁。黒い胆汁というのがメランコリーの語源になった。コリーというのは胆汁という意味です。リュウマチというのも古代ギリシャの単語で、流れるものという意味です。あっちこっちに症状が流れていく。
一中 症状が移り変わるんですね。
津田 漢方でも「四肢流注」と書いて、リュウマチのことを表していた。東洋医学の五行説、気血水とかですね、自然にある要素で人間の健康を説明していた。
一中 「この体は地水火風 、死ぬれば空に帰る。五生七生」 と近松門左衛門が『心中天網島』で書いています。
津田 地水火風、大地と水と火と風なんですね。
一中 古代ギリシャと古代中国との世界観が共通しています。人間考えることが一緒ですね。
津田 大自然を観察していく中で、人間の体の健康を考えるということです。西洋の近代医学は解剖や顕微鏡に代表されるように、人体をバラバラにしていく分析的な思考法を採りますが、伝統医学は空を見たり流れる星を見たり風を感じたり焚き火を見て、世界の構造と人体とのアナロジーを考えたわけですね。
一中 江戸時代って、誰でもお医者さんになれたと言いますね。
津田 そうなんです。国が定める医師免許がなかったので、皆さんどういうところでお医者さんの腕前を判断したかというと、自分が師事した先生にお免状を書いてもらって、そのお免状を表の方に出しておくそうなんですよ。お免状を書いた先生が有名な医者であればあるほど、「この人のお弟子さんだから信頼できる」ということで門前市をなすようになるわけです。
一中 一中節で言うと、名取みたいなもんですね。
津田 そうですね。みんな字がうまいんですよ。字がうまくないとお弟子さんも取れないんですね。
一中 常磐津の中に「誰々様のおさじでございます」というセリフがありますが、おさじとは主治医ですね。お大名の。薬はさじ加減が大切ということですね。外国の医療と比べてどこがよかったのでしょうか。
津田 中国からの豊富な薬草と学問も入ってきて、それにプラスして西洋医学も相当勉強していたんです。杉田玄白たちの『解体新書(ターヘルアナトミア)』が有名ですね。西洋のお薬も使っていた。シーボルトは医師で、出島に来ていろいろ教えていた。シーボルトが使っている目薬はベラドンナで、散瞳薬(さんどうやく)という瞳孔が開く薬だった。日本では手に入りにくいので非常に珍重されたんですけれども、実際に弟子入りしてみると「あいつは大したことがなかった」と本間棗軒(ほんまそうけん)という日本の医者が書いてるんですね。とにかく痛み止めとか咳止めとかに麻薬を使いまくって、患者が死んじゃったりしていると。「悪用癖」「こういう医療をやっていたんじゃだめだ」と書いてあるんです。本間棗軒は、『瘍科秘録(しょうかひろく)』という外科の秘伝書を書いたんです。この人はすごいドクターで、『内科秘録』というのも書いているんですよ。全部できるんです、昔の人は。手術もやるし伝染病も見るし、すごいですよ。そういうように患者さんをずっと見ていると、中国から入ってきた昔ながらの文献のように治療していくのではうまくいかないとか、実際見たらこうだからここはこう治すべきじゃないかと書いてある。古いものにただただ従うだけでもないし、新しいからといって飛びつくのでもなく、「親試実験」、すなわち自分が見た経験と照らし合わせて、古典も批判するし西洋から入ってきた知識も批判する。
一中 ただありがたがるんじゃないんですね。
津田 「シーボルトはだめじゃないか」と言いながら、「あの人が使っている目薬は日本にないものだから、日本で似たような作用があるものを探そうじゃないか」といろんなことをやっているんです。
一中 柔軟ですね。頑なじゃないんですね。
津田 シーボルトに弟子入りした本間棗軒は、世界初の全身麻酔手術を成功させた華岡青州にも師事していたんです。だからシーボルトのことを絶対視せず自由に批判できた。それだけでなく、彼は水戸の出身だったから、学問のバックボーンがしっかりしていたんだと思いますね。水戸は、本当はすごいところだった。
一中 水戸は、学問が非常に盛んだったんですよね。
津田 学問はすごかったですね。今残念な感じになっているのは明治政府に恨まれたからです。水戸をいちばん恨んでたんで、寂れさせたんですね。同じことは会津にも言えます。
一中 水戸に行く常磐線は、線路を蛇行させてすごく乗りにくくしたと言いますね。
津田 明治政府があんなことをしなければ、水戸は今ごろニューイングランドみたいになっていた。ボストンみたいになって、世界に名だたる病院ができていたと思います。 文化施設もできていたと思います。
一中 日本の医学を否定したのも明治政府ですね。
津田 そうです。 とにかく全部否定ですよね。
一中 江戸時代のものは全部否定して新しく西洋から入ったものだけを信じる。すごくそれが尾を引いていて、今も西洋医学が東洋医学を否定する。
津田 日本が外から入ってくる物をどんどん柔軟に取り入れてきた国だということもあるんですけれども、そういうことの副作用が出ている。
一中 先生みたいな方が現われる時代になっている。それも日本で歴史的にたびたび起こることです。遣唐使をやめて菅原道真が国風文化を築いていったのも、外国の文化を取り入れていたからです。今、反省の時期になって、日本の古い文化のよさにみなさんが気づいて、これから日本の文化の第2期国風化で外国の文化と融合させて、さらに高度なものができるんじゃないか。そういう空気があります。
津田 今はインターネットで、中国の文献もヨーロッパの文献もすぐ取り寄せられます。歴史的な医学文献の検索が可能になっています。そうなるとどこの時点で考え方が変わったか、全部分析ができるようになっている。それ自体が研究できるようになっているんですね。昔の人の水準ってすごく高いんですけれども、今は昔の人ができなかったこともできるようになってるわけで、単に昔の人のいうとおりにするわけではない。音楽の世界でも、日本の昔からの楽器を触ることもできるし、海外から来た楽器もあって、そういう時代に生まれたというのはアドバンテージですよね。
東洋医学の治療を取り入れたわけ
津田 私が東洋医学を取り入れようと考えたのは、現実に目の前に来る患者さんのニーズに答えられないと思ったからですね。西洋医学的なことだけではね。西洋医学でしか解決できないこともあったわけですが。だからこそ江戸時代のお医者さんも文句を言いながら西洋医学を勉強していた。果ては全身麻酔で手術をするようになったわけですから、華岡青洲のように。
一中 日本で全身麻酔の手術が成功してから、アメリカで成功するまで何十年もかかっているわけですよね。華岡青洲って、先生にうかがうとそんなにすごい人なんだって思うんですけれども、『華岡青洲の妻』という芝居で見ると、嫁姑の間に立ってただオロオロしている情けない男というイメージなんですよ。ところで、三味線をやってみようと思われたのはどうしてなんですか。もともと西洋音楽をやっておられたんでしょうか。
津田 元々バイオリンをやっていました。
一中 共通するところはあるんですか。
津田 音楽も西洋の捉え方と東洋の捉え方の違いが、医学の捉え方と非常に似ているところがあってすごくおもしろいんですね。一中先生にお尋ねした質問の中で三味線の調弦がありました。バイオリンだと音叉とかチューニングメーターとかで、440hzという周波数で合わすんですけれども、三味線はどうやって合わせるんですかと聞いたら、「楽器によってそれぞれ周波数が違います」と。楽器自体のいちばん響く音に合わせるんですね。
一中 何人か舞台に出るときは、中心になる人に合わせるんですけれども。それでもちょっとずれてるんです。バイオリンだったら基本になるG線ですか、いちばん低い音が、三味線の場合には決まっていないんです。適当でいいんです。空間とか楽器のご機嫌とか歌ってくれる人の声の調子とかで決める。
津田 温度とか湿度とかでも左右されますよね。
一中 湿度が高いと湿った音というか、糸が水分を含みますので重くなる。そういうときはちょっと高く音を合わせる。というか、高くなっちゃうんですね。ピッチが決まってない。
津田 それは医学もまったく同じで、西洋医学は基準値というのがあって、肝臓の数値はこうで、その範囲に収まっているのが健康という考え方です。東洋医学はそれがいつもゆらゆらしているんです。その人にとって、いちばんパフォーマンスが出るような体調にしましょうっていう考えです。 例えばすごく頑張らなければいけない、ストレスがかかってる人だと、ストレスに合わせて健康状態を持っていくわけですね。患者さんが「元気が出ません」とおっしゃると元気が出るようなお薬を使っていく。ひょっとしたら西洋医学としては血圧を上げすぎているということになる。ずっと上げっぱなしにすると疲れちゃったりするから、どこかで緩めないといけないんですけれども。患者さんのニーズに合わせてお薬を出すやり方は、「健康は、その時点その時点で変わっていく」という考え方からなんですね。
一中 それも日本の音楽の考え方と同じで、臨機応変ということですね。
津田 いつも同じじゃなくて。 一人一人に合わせてお薬を出したりするわけです。 インフルエンザの患者さんが10人やってきたとしても、10人ともお薬が違ったりする。そういうことは西洋医学では考えられないですね。
一中 お話を伺っていると「それは一人一人違って当たり前でしょ」と思ってしまいますが。
津田 西洋医学だったら、インフルエンザはインフルエンザウイルスの仕業だから インフルエンザウィルスをやっつけるお薬を出しましょうとなる。ある人は熱がすごい。ある人は全然熱は出ないんだけれども、元気が出なくてぐったりしている。ある人は汗をいっぱいかいて、ある人は汗が全然出ない。西洋医学だと全部同じお薬です。それはピッチが440hzというような感じですよ。ところが漢方だと、インフルエンザで高い熱が出る人には熱を下げる方向のお薬を出して、熱がうまく上がらなくて元気がない人には熱がもう少し出るようにお薬を出す。汗をいっぱいかいて疲れちゃってという人には、汗がおさまるようなお薬を出したり。みんなインフルエンザなんだけれども、お薬が違う。いろんなやり方でインフルエンザ・ウィルスと体が一生懸命戦おうとしている。体がなんとかやろうとしていることを後押しするという考え方ですね。それはインフルエンザじゃなくても、違うウイルスでもやることは同じなんです。西洋医学が困っているのは新種のコロナ・ウイルスというのがきたからですね。インフルエンザ・ウイルスのお薬はあったけれども、コロナ・ウイルスのお薬は一から作り直さなければならない。それはとっても時間がかかるわけです。東洋医学だとインフルエンザが入ってこようがコロナが入ってこようがばい菌が入ってこようが、一生懸命体が追い出そうとしている努力の後押しをしてあげる。どんな病原体が入ってきても何がしか作戦を立てられる。一中 そうか。 症状に対して薬を出すわけですね。
津田 症状と言うか患者さんの戦い方に対して、ですね。
一中 コロナが流行りだしたころ、コロナにもしかかって咳が出てきたら、麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう)というのと小青龍湯(しょうせいりゅうとう)、この二つをまず飲めば症状が確実に治ると。とりあえず症状が治ればいいわけですからと教えていただいたんです。それを僕いつも持っているんです。 そういうことなんですかね。
津田 本当は患者さん一人一人にお薬を変えないといけないんです。インフルエンザだろうがコロナだろうがバイキンだろうが、悪いものが入ってきたときにいちばん最初に起こる反応はだいたい一定している。だからそれを後押ししてあげるお薬は最初の段階だと同じお薬です。かかったかかからないかわからないくらいのときは、これ飲んでくださいということが言えるわけです。逆に、西洋医学には効率の悪さがある。
一中 すごく時間がかかっちゃうわけですね。
津田 全然わからない要素が入ってきたら、それに対するワクチンなり治療薬を作るとなると、すごい時間がかかる。
一中 どんどん未知のウイルスが出てくるわけですよね。
津田 漢方だと、変異株も全然関係ないです。何が入ってくるかじゃなくって、入ってこられた側がどう反応しているかに合わせてお薬を出していくわけですから。
一中 発想が違う。
津田 一人一人に対して違うお薬を出すというのが、全部の楽器が違う調律になっていく話とアナロジーになっている。
一中 基準値を設けるとか、このウイルスにはこの薬と決めて画一化するのは西洋音楽に似てますよね。日本の楽器は個別の存在で、一人一人が違う譜面を自分で作るし、みんなが共通にわかる譜面というものがない。譜で勉強しなさいということはないわけですから、一対一で教えるしかないんですよ。
津田 西洋音楽は楽譜がすごく大事ですね。
一中 楽譜になってないと、一緒にできない。
津田 でも江戸時代の楽譜には、テンポだとかそういうものの指示は全然ないんですよね。あれは音の高さがかろうじて書いてあるくらいで。
一中 だいたいおさえる場所が書いてあるんです、三味線の。
津田 リズムとかは全然書かれてない。それも面白いなと思って。西洋音楽だとメトロノームという、絶対的なリズムで演奏できるように工夫されて書いてあるわけですけれども。
一中 僕は高校生の時に三味線の基礎練習みたいなのをメトロノームで弾いてみたことがありますが、一瞬も弾けなかったですね。日本の音楽ではなくなってしまう。だから普通に弾いているときは均等リズムじゃないんですね。おそらく日本の考え方は全部そうなんでしょう。数学でも微分積分を西洋の何十年も前に解いていたと聞いたことがあります。日本の和算というのは問題を絵馬に書いて下げておいて、みんなが競って解いた。今のゲームみたいに。普通の庶民の知的レベル、識字率が群を抜いて高かったということですね。みんなが寺子屋に行って読み書きそろばんをやるわけですから。
津田 どこに行っても同じ時間が同じスピードで流れているということが、西洋の基本的な考え方なんですよね。どこでも1秒は1秒の速さで流れて、1時間は1時間の速さで流れる。1m はこの長さで、周波数はこれで。世界中のどこに行っても同じだというのが西洋の考え方だと思うんです。人間の体も平熱が36°Cというのが、世界中のどの人を測っても同じだという考え方になるでしょうね。東洋はそれを採用しなかった。興奮してたら熱も出るだろうし、寝不足だったら血圧も上がるだろうし。時間の流れ方も本当は違う。天気の悪いときの時間の流れ方とか、真っ暗になったときの時間の流れ方とか、物理的な話は別ですけれども、主観的な心理的な時間は伸び縮みするだろうし。空間の大きさも、実は小さく見えたり大きく見えたりするんです。
一中 アインシュタインが相対性理論を説明するときに「大好きな女の子を口説いているときの10分というのはものすごく短く感じられる。焼けた石の上に座っている10分というのは死ぬほど長く感じられる。それが相対性理論なんだ」と言ったというのを読みました。今おっしゃったように、相対性理論だと時間の流れがどこに行っても同じじゃないわけですよね。宇宙の空間もすごいスピードで動いているという考えで、時間の流れが物理的に違うことを証明したわけですよね。それは違って当たり前でしょうと感覚的に捉えているのが日本人ですね。
津田 本当にそうだと思いますね。アインシュタインの時代になるまで誰も思いつかなかったというのは、その前のどこも同じ時間と空間の流れ方だという思い込みと考え方が西洋を長きにわたりものすごく強く支配していたからだと思いますね。
一中 西洋医学を勉強してこなすことだけでもものすごく大変なのに、その上にさらに漢方を勉強するのには、よほど能力が高くないとできないですよね。音楽も日本と西洋、どっちかをやるだけでも精一杯なんだけれど、その上に他のものもやるというのは、興味を持っていて好きなことだし、なんかこれで解決できないかという気持ちがあるからだと思うんです。先生の場合には、患者さんをとにかく楽にしてあげたいというその気持ちが、西洋医学だけじゃだめなんだということにつながったのか。先生はたくさんご著書がありますが、いずれもお話がお上手ですよね。西洋医学が最先端なのに、なぜうまくいかないんだろう、漢方だったらなんとかなるかもと思わせられます。患者さんを本当に治してあげたいという情熱の強さなんですかね。
津田 それはありますね。日本の医学は、日本人の患者さんの性質に合わせて発展してきたものなんですね。そういうものを使わないといけない場面というのが絶対あるはずなんです。例えば患者さんって病気を治したらいいわけじゃなくて、説明を求めている。「なんで私はこういうことになったんだろう」という疑問に対する説明です。「これ飲んだらよくなるから、言うとおりにしていたらいいんだ」と答えていたのではダメです。でも、「どうして私はこんなに具合が悪いんでしょう」というのを西洋医学的な言葉で説明すると、ものすごく時間がかかって、しかも分かりにくい。ところが、「気の巡りがうまくいかないんです」とか「この辺の血の巡りがうまくいかなくて」と、そういう日常の単語で話すと、すっと納得してもらえたりするんですね。「私もそんな気がしてました」という話が出たりします。
一中 納得するだけで、かなり解決になりますね。
津田 客観的な情報じゃじゃなくて、主観的に訴えかけてるからですね。自分の体の内部の感覚、そこに伝統医学とか古い医学の言葉が寄り添っている、フィットしているということです。「遺伝子の何番染色体がどうでこうで」とか「塩基の配列がどうでこうで」とかいう説明は、ピンときませんね。こういう説明の仕方は、自分の体で感じている感覚には無いジャーゴンの羅列になってしまいがちだからです。なんとなくこういうふうに感じていたというところにぱっと言葉がはまる。それが古い医学の得意とするところなんです。
一中 なるほど 。日本人に納得される真理があると、治りが違いますね。
ニュアンスを確実に伝えようとする日本の音楽
津田 外国から来た患者さんには、むしろ西洋医学の専門用語をバラバラバラバラと 言った方が逆に納得してもらえます。西洋医学の用語は、日本語に訳してしまうと漢字だらけになって日常言語から離れてしまうのですが、西洋の日常言語とはもう少し近い関係にあるんでしょうね。専門用語も全然気にせず使った方が、そのまま納得してもらえますね。楽器もそうだと思うんです。バイオリンとか西洋の楽器って石造りの建物で乾燥したところで鳴らすとすごくよく鳴るし、そんなところで練習するとうまくもなると思うんです。だからこそ440 Hz とか楽器の音をぴったり合わせて、2倍音や3倍音を聞いて楽しんでいると思うんです。
一中 今のお話は、西洋の音楽の本質を本当によくついています。
津田 私は西洋音楽が好きでよく聞いているんですけれども、まず楽譜に忠実に演奏して、音程やリズムをぴったりそろえてハーモニーを作り出す。でも楽譜は音楽を完全に支配しているわけではなく、演奏家が微妙にテンポやタイミングをずらしたり、音の「かすれ」みたいなものがでたりして、音楽が「意味」を持つようになります。まったく同じ旋律でも、演奏家というのは大したもので、悲しそうにも楽しそうにも奏でることができます。これは楽譜では表現しきれない、ニュアンスみたいなものですね。西洋音楽ではこのニュアンスが、オーケストラや指揮者の個性だとか解釈だとか言われるものですね。楽譜に書いてないものを一生懸命伝えようとしていて、そのニュアンスの違いが演奏者の違いになる。この指揮者はいつもこうだな、あの指揮者はずいぶん新しい解釈をしたなという違いが、西洋の、特にクラシック音楽を聴き比べる楽しみの一つです。他方、日本の音楽は音の高低やリズムをぴったり揃えることに、西洋ほど拘泥していないように思います。日本の風土や建物の構造では、音の反響を楽しむというよりも湿気の中で音がしっとり伝わる。ぴったりヘルツが合って倍音を楽しむ楽器は必要とされなかったんじゃないかと思うんです。 だから音叉とかで音程を全体的に合わせることは、日本ではあまり意味を持たないんですね。それよりも日本の風土で暮らしている感覚、主観、暮らしとかが入っていくんでしょうね。時間も自由に伸び縮みする。遅いテンポにしたり、早いテンポにしたり、自由自在である。一中先生のお稽古では、最初の段階からニュアンスをすごく正確に伝えようとしています。私は日本の音楽にそれほど馴染みがあるわけではありませんけれども、ニュアンスとか「解釈」については演奏家間の違いは西洋に比べて小さいのではないでしょうか?その代わり、聴衆やその場の雰囲気に合わせて、音程やテンポは大きく変わる。とにかくニュアンスを揃えるほうが大事で、音楽の物理的な体裁を整えるのは二の次です。だから日本の音楽では、楽譜というものの「地位」が、西洋音楽よりも低いということになります。西洋音楽はニュアンスが皆バラバラで、驚くほど違う。それが西洋音楽のおもしろいところですね。同じ楽譜なんだけれども全然音楽が違う。日本の音楽はニュアンスの部分はかなり共通していて、聞くたびに全然テンポが違うとか音程がずれていたりとかとかはある。でも機微みたいなものを確実に伝える。そういうところがあるんじゃないかなと思いました。
一中 そういうところはゆるぎないもので徹底的に伝承されていて、自分の主観を入れてはいけない部分です。
津田 演奏家の名前がないというのは、もちろん何代目が弾いたというのはあるんでしょうけれども、お家芸というのか演奏家の個性で売ってはいないところがあると思いますね。
一中 本質だけを見ていく。自分を表現するのではなくて。先生は西洋音楽も日本の音楽も両方お好きですね。バイオリンも演奏される。
津田 いえいえ。下手くそなんですよ。
一中 音楽に対する観察も並外れていますね。日本の音楽家で医者というのは聞いたことがないですけれども、西洋音楽ではシノーポリが精神科医でしたっけ。
津田 脳外科だったか精神科だったかですね。
一中 西洋医学だけを勉強しているお医者さんが三味線を弾くというのとは違うかもしれないですね。そういう時間はどうやって。
津田 興味があるからですね。西洋医学の先生のように毎週毎週山のような文献を読むのは、私はやっていないかもしれません。みんなが同じことを言うようになったからこれは信用していいかな、というのはあります。最先端の話は次の日には否定されていったりしますから。勉強はちょっと遅れているぐらいがちょうどいいかもしれません。
一中 先生とお話ししていて、思い込みみたいなことを考えたんです。癌になるんじゃないかと思っていると癌になる確率が高くなるし、絶対ならないと考えているとならない。癌になるんじゃないかなと思えるのは、癌になる要素が既にあるじゃないかなと。
津田 逆なんじゃないですか。 癌になるんじゃないかなと思うから癌になるんじゃなくて、癌になってからそういうように思うようになるんじゃないか。既に癌になっていて、それを何となく感じている。時系列が逆ではないですかね。まず癌になった時点がその前にあって、それで癌になったような気がするっていう話をしたんです。
一中 逆に癌になってるのに癌じゃないと思っていると、悪化しないということはありませんか。癌ってなったり治ったりするらしいですから。
津田 それはどうなんでしょうね。人によると思いますね。
一中 芸をやっていると、直感的にお医者さんとお寿司屋さんは見分けられると思っているんですよ。見た瞬間にこの先生だったらかかりたいというのがわかる。相性もあるでしょうけど。自分がかかっているお医者さんを全部信用することが治るのにはいちばんいい。「こういうことされてるけど大丈夫なのかな」と思うようならその先生にはかからない方がいい、同じ薬でも効き目が違う」と言われたんです。「漢方の話から説明してもらうと「ああそんな気がする。この先生わかってるな」と信頼する。そういう心理的な要素はどうなんでしょう。
津田 それこそが先ほどの「ニュアンス」の部分ですね。音の高さやリズムが薬であったり医療の物質的な部分に当たる訳ですけれども、治療はそれだけで成り立っているわけじゃなくて、それ以外の心理的な効果ですよね。その支えがないと治療は非常に困難です。極端な話をすると、治療自体はうまくいっていなて結果がうまく出せなくても、患者さんは納得して下さる場合もある。それはニュアンスが伝わっているからだと思うんです。こう言ったら言い過ぎかもしれないんですけれども、ゴールは物理的な面ではなくて、ひょっとしたらニュアンスの面かもしれませんね。
一中 この先生に診てもらえば殺されてもというのは言い過ぎですが、それでも診ていただこうと思えるということが治るということだと思うんです。なんかだめだなと思ったらだめじゃないですか。相性もあるでしょうしね。
津田 こう言ったら身も蓋もないんですけれども、人間いつかは死んじゃうので、満足して死ぬのか不満を残すのかっていうところで医療の結果が計られるとすると、ひょっとしたら癌が消えるとか病気が治るっていうことが最後ではないかもしれない。満足して人生を送れる死ねるというのが医療の最終目的であるとすれば、ニュアンスか物理的な面かというと、心理的な要素の方がウェイトは多いのかもしれません。音楽もそうで、チェリストのミッシャ・マイスキーだったと思いますけれども、「音楽は手段にしかすぎない」とおっしゃったんです。伝えるということができれば、音楽でなくてもいいんだと。
一中 いい時間を作る。それが後々の幸せになってくれれば。今こうやってお話しさせていただいて、これ即興演奏です。今日はだいたいこんなことでやろうで話が盛り上がって、ずっといい時間を作れていますけれども、これ自体が音楽だと思うんですね。
津田 三味線のお稽古も、最初にニュアンスを持ってくるということが新鮮です。西洋音楽は音階練習とかきっちりリズムが刻めるとか、基礎練習を泣くほどやって泣いて泣いて泣いて最後に笑うみたいな、つまらないバイエルを一生懸命やって山ほど練習を積んだ上にようやくニュアンスが乗っけられるとことになるわけです。一中先生の場合は、最初にニュアンスから入るというのがすごいなぁと思って。それが日本の楽器だとできるんだなと思いました。
一中 自分が西洋の音楽をちゃんとやったことがないので、意識していませんでしたけれども。
アメリカでも取り入れられている鍼灸の現在
津田 西洋医学は常に目に見える結果を出すことを求められます。癌が何パーセント小さくなったとか、検査値が何パーセントよくなったとか。数字に走ると失われていく部分が絶対ありますよね。この検査のポイントが平均1%少なくなりました、でも医療費が100万円増えます、みたいなね。本当にお薬屋さんってそうなんです。そのパーセントを少なくするためにどれだけのコストがかかっているのか。それだけのコストを払ってしまうと患者さんの満足度が下がるんじゃないか。患者さんの満足度を考えると、前の治療の方がいいこともある。
一中 満足度ですね。 話をうかがっていると本当に当たり前のことなんですけれども、なかなか全体的には当たり前じゃないですよね。まして一日に何十人も次から次へと診察する状況だと、やっぱり数値で見ちゃうでしょう。先生のようなお考えの方は、他にもいらっしゃるんですか。
津田 いっぱいいると思いますよ。西洋医学しかしてない人でも、近いことを言ってる人はいっぱいいると思う。ただ、患者満足度の問題を、医療の地域性とか歴史性に絡めて考えるというような人は少ないかもしれない。どこに西洋と東洋の考え方の違いが表れているかとか。歴史みたいなものと関連付けて考えるという人は少ないのかもしれないです。
一中 邦楽の方でもそうですね。三味線弾きで西洋音楽が好きというのは本当に少ないんじゃないかな。そのほうが、幅が広がっておもしろいと思うんですけれどもね。
津田 「患者さん思いの治療をしましょう」と言うと、すごくいいことのように聞こえますが、いろんな考え方があって、患者さんのわがままにずっと付き合うのが本当にいいかどうか、そういう話もありますし。こっちの体が持たない。あと、医療費の問題もあります。日本は国民皆保険の国なので、3割程度の自己負担で治療が受けられます。のこりの7割は本人ではなく社会が負担している。そうなると、いくら本人が希望したとしても、不当にコストの高い治療を選択するわけにはいかなくなりますね。私の専門の膠原病は、いくつかの病気が難病(特定疾患)に指定されていて、さらに手厚い補助が受けられます。難病というと「治り難い病気」と誤解されてしまうのですが、最近はとてもお薬がよくなって治療できることが多くなってきました。 なので「難病」という表現で悲観的になる患者さんには、と「治療ではなく原因究明が難しい病気なんですよ」と説明したりしてます。
一中 リュウマチもそうですか。
津田 そうですね。リウマチは膠原病の一つです。怪我をするとかさぶたのあとにできてくる、膠(にかわ)のような組織、それがコラーゲンです。このコラーゲンの日本語訳が「膠原」なんですね。膠原病の患者さんの組織を顕微鏡で見ると、体中にコラーゲンがいっぱい出てくる。それで、膠原が悪いんだと考えて、膠原病と名前をつけた。 ところがこれは大きな誤解で、コラーゲンが原因なんじゃなくてコラーゲンを作らないといけないようになることが問題だったんです。体に傷がついている。あまりにも傷ついた場所が多くて、応急的に直すために一生懸命体がコラーゲンを作って直す。最後に亡くなったご遺体を見るとコラーゲンだらけになっている。病理学者の先生が、「コラーゲン病」という名前をつけちゃった。自分自身の免疫が自分自身の体を傷つけてしまう、それがそもそもの原因なので、本当は自己免疫疾患と言ったほうが実態に合うんですが、「膠原病」という名前にすごく馴染みができてしまって、なかなか変えられないんです。
一中 癌という名前も字もよくないですね。笑い話ですが、「癌をポンって変えようよ。ポンなら治りやすいんじゃないか。国際ポン学会とか」って。笑いっていうのは免疫力を高めると言いますから。そういえば、先生に見ていただくにはリュウマチにならないといけないんですか。
津田 漢方やっていますんでね、普通の内科的なのも診ています。残念ながら NTT 病院では鍼灸はやれないんです。保険の枠内でやると鍼灸師の方にお支払いするお手当が、本当に雀の涙みたいになっちゃう。ほとんどボランティアみたいになっちゃうので、なかなか保険の枠内では使えないんです。将来的には混合診療といって、保険と実費の診療を自由に組み合わせられるようになると、病院の中でも自由に鍼灸が使えるようになると思いますけれども。ゆくゆくは病院の中で鍼灸を普通にやる時代が来ることを見据えて、数年前から医療鍼灸協会という組織を立ち上げて、病院で治療ができる鍼灸師を育成する活動を始めています。
一中 チームを組んで、患者さんに対してこの人は鍼がいいんじゃないかとかこの人はどうするということを、総合医療って言うんですか、アメリカは進んでいるように聞きますね。
津田 アメリカでは鍼灸をやっています。特にエイズの治療でやっているみたいですね。アメリカで鍼灸が流行るようになったきっかけは、米中の国交正常化ですね。1970年代のことです。アメリカから記者がいっぱいやってきて、中国で取材しているときに鍼麻酔で手術をするのを見せた。鍼でプスプスと刺したらズバッと切っても患者さんが痛がらない。頭蓋骨が開いていても喋れる。「今どの辺ですか」みたいな話をしている。それを目撃して、新聞記者たちがびっくりしたんですね。麻酔だったら意識がなくなりますから、鍼を刺してさらに麻酔をしてたらわかるわけですよ。患者さんが喋ったりはできないですから。痛がらない人がいる理由もないですから。
一中 神経がない人もいないでしょうからね。痛みは鍼で止められるんですか。
津田 鍼で痛みが止まったのを見て、アメリカの記者が腰を抜かしたんですね。そこから一気にアメリカで鍼灸をやる人が増えたんです。
一中 日本の方が昔から鍼灸があるのに。
津田 鍼麻酔は実は非常に人を選ぶんです。効く人と効かない人がいるんです。非常によく効く人でやるとそういうことができる。みんなにはできないんですよ。一部分の人ですね。
医学史と連なる縁を感じて
一中 『三国志』の曹操(そうそう)がすごい頭痛持ちで、これは絶対脳腫瘍だと考えた華佗(かだ)という侍医が「頭を開けて手術しないと助からない」と言ったところ、「俺を殺すつもりか」と曹操が怒って華佗は処刑されてしまったというお話がありましたね。曹操もまもなく脳腫瘍で死んだ。その頃からもう開頭手術というのがあったんでしょうか。『三国志』は卑弥呼より前の話ですからね。
津田 麻酔はしていたって言われていたんですね。漢方薬で麻酔する技術があったって。そのことを華岡青洲がすごく気にかけていて、華佗の時代に麻酔ができたんだったら我々も麻酔ができるはずだと考えて、いっぱい文献を取り寄せて世界初の麻酔を成功させたということなんです。
一中 遺跡から出てくる頭蓋骨に開頭手術をした跡があると言いますね。先生は歴史がお好きなんですよね。
津田 私の本籍地は京都の東洞院三条(ひがしのとういんさんじょう)というところで、ここが日本の医学にとって非常に大事なところなんです。そのことには後から気がついたんですけれども。中国の医学そのままが日本の漢方になっているわけじゃないというお話をしましたが、日本独自のやり方、日本漢方を作ったというお医者さんがいます。江戸時代中期の吉益東洞(よしますとうどう)というお医者さんです。1700年代の人ですね。中国のやるとおりやっていたんでは病気がよくならないと、日本独自の医療のやり方を目指した。ところが、東洞は医学の教科書とか歴史の教科書にも全然触れられていなくて。それは日本の歴史教育の大きな問題だと私は思っているんですけれども。吉益東洞という人はもともと為則という名前で、広島の出身だったと思います。京都の東洞院で開業したので、東洞という名前にしたんです。東洞院というのは長い通りで、三条も四条も五条もあるのに、三条で開業していた。 私の本籍地も東洞院三条で、そんなに意識はしていないんですけれども、地縁みたいのがあるのかもしれませんね。非常に歴史の古いれんが造りの郵便局があるところです。烏丸通りより一本東で、烏丸三条のすぐ近くです。
一中 初代一中の生家があるのが、京都の御池通り堺町なんです。近いといえば近いですね。 初代一中は1724年まで生きましたから、まさにその時代ですね。
津田 完全にかぶってます。同時代人ですね。
一中 もしかしたら初代一中が診ていただいていたかもしれないですね。
津田 京都が文化の中心だったということですね。
江戸時代の真ん中が文化の曲がり角
一中 京都の人は結構新し物好きです。古いものを残しているという自信があるから飛びつけるんですよね。先生のご出身の京都大学医学部では、漢方はどうなんですか。
津田 京都大学では漢方は全然だめです。ようやく最近になってそういう部門を作ったそうですけれども。日本の大学の中でいちばん遅れましたね。でもノーベル賞が出ています。医学と生理学と二つの分野で出ました。山中伸弥先生と本庶佑(ほんじょたすく)先生、利根川進先生。
一中 霊長類研究の西原智昭先生と親しくしているんですが、やはり京都大学出身で、今コンゴ共和国に行ってらっしゃいます。最近はヨウムという鳥の保護運動をされています。コンゴ共和国の自然環境と野生動物の保護ですね。コンゴ共和国のブッシュに住んでいるマルミミゾウという象の牙しか三味線のバチにならないんです。象牙が柔らかいからいい。湿気があるところにいるゾウだそうです。それも絶滅しそうなんですね。人間がブッシュをなくしちゃってるから。
津田 私自身が京大とのつながりを感じるのは、どっちかと言うと人文研(京都大学人文科学研究所)とか図書館ですね。医学史の文献が非常に多い。漢方の文献もあります。
一中 そういう資料もあるのに漢方が盛んではないんですか。
津田 医療としてはですね。医学の歴史は文系ですからね。吉益東洞のお家の方はまだ岐阜の大垣のほうにいらっしゃるらしいです。
一中 エポックメイキングな方なのに、なんで我々知らないんでしょうかね。
津田 今の国家体制の話と関わるわけです。今の国家は明治政府と明治維新を礎にしているわけですから、国のすべてが1868年から始まっている、1868年で大きな節目があった、ということにしたいんですね。歴史の教科書なんかもみんなそうなっている。でも実は、江戸時代のど真ん中くらいに非常に大きな変わり目、文化史的な断層があったのではないか、という説があります。そのうちのひとつが吉益東洞の医学だった。
一中 時代が合いますね、初代一中と。平和が100年続くと、たいへん文化的な変革が起こる。みんなが文化的なことにじっくり取り組めるようになるからです。
津田 近松門左衛門とかそういう人が出てきて。
一中 松尾芭蕉もそうですし。
津田 文化史的には1868年の前と後は連続していて、むしろ江戸時代のど真ん中に非常に大きな曲がり角があった、そういうふうな歴史の教え方をしている人はとても少ないですね。その話を最初に聴いたのは、解剖学者の養老孟司先生からです。私が大学の1年生か2年生の時です。市民講演会みたいなところで養老孟司先生がそういうことをおっしゃったんです。「1700年代の真ん中ぐらいで大きな文化的な節目があった」と言われたんですね。養老先生は解剖学の先生ですから、解剖学の視点からしかお話をされないんですけれども。腑分けをやった杉田玄白は、吉益東洞の弟子筋にあたる人なんです。人間を解剖して、体の中がどうなってるのか見ることを始めたのは、1700年代なんですね。養老先生によると、当時は専門家だけが見るのではなくて、見世物みたいになっていたらしいです。人々の意識が大きく変わったとおっしゃる。儒学とか朱子学とか、政治思想史なんかを調べてみるとやっぱり同じようなことがあって、荻生徂徠(おぎゅうそらい)という人が出て、倫理や道徳と法律とは別にして考えた方がいいんじゃないかと言った。「封建制度の基本に宇宙の摂理があるというが、孔子さんはそんなこと言ってなかったじゃないか。孔子はそもそもどういうことを言っていたんだ。孔子が言っていた道徳的な話と現実に行われている政治は分けて考えましょう」ということです。
一中 それまでは朱子学が政治に反映されて、それで政治を行っているということになっていたんですね。
津田 四季の移り変わりと太陽の運行、月の満ち欠けと潮の満ち干、北極星があってその周りをまわる星空の世界―――宇宙には秩序がある。だから人間世界も同じような秩序があるべきだという考え方が12世紀に成立した朱子学なんです。でも、荻生徂徠に言わせれば、儒教の元祖である孔子の『論語』を読んでも天文学は出てこない。そんなことあとから人が言ったことに過ぎない。だから朱子学の考え方を絶対視しなかったんですね。いちばん象徴的なのが赤穂事件です。討ち入った四十七士を助けるか切腹させるか、大きく意見が分かれたんです。朱子学の立場の人は助命嘆願です。「道徳的な秩序を守ったんだから彼らは見逃してやるべきだ」と。荻生徂徠はそうじゃなくて「忠義者だったかもしれないけれども、彼らは法律を破っている」と言った。徒党を組んで私宅に押し入って相手を殺害したわけですよ。将軍の命令でもないのに。
一中 明らかに罪なんですね。
津田 それは形式的にでも罰しないと、ルールがぐちゃぐちゃになって国家が運営できない。道徳倫理と法律は分けて考えましょうと言ったんですね。結局、将軍綱吉はそっちの方を取ったわけです。そこで歴史と考え方が大きく変わった。
一中 四十七士に加わらなかった浪士たちは後で非常につらかったらしいですね。そこで考え方が大転換したわけですね。綱吉は「武家諸法度(ぶけしょはっと)」を変えましたから。明治時代は江戸時代の医学の否定がすごかったんですよね。
津田 制度的には漢方医は全然医者として認められなかった。とはいえ明治の医療は、初期には相当漢方医がやっていたんですね。医師免許とは関係ない次元で。江戸時代に活躍していた医者が明治時代にも活躍していました。
一中 治療しちゃいけないというわけじゃなくて、存在は許してたんですね。それは僕たちが音楽家として存在できるのと同じだと思うけれども。漢方で治療したらいけないとか三味線を弾いたら死刑になるとか、そこまではやらなかった。
津田 でも国家がバックアップしなかった影響というのはすごく大きくて、食べていけないことになるわけですよね。文化は1868年でぶつっと切れてはいないです。歌舞伎でも河竹黙阿弥が相当長いこと続きましたけれども、やっぱり国家からの保護が得られないというのは芸能を蝕んでいってしまいますね。
一中 それは明治政府が西洋医学は正しくて合理的、漢方は非合理的で迷信みたいなイメージを植え付けた。政権が変わるということは、そういうことなんだと思いますけれどもね。
津田 黒船の時代から西洋医学という斬新で素晴らしいものが日本にやってきたかのように思われていますが、西洋医学は結果を出せる。そういうふうにようやくなってきたのは本当にごくごく最近の話です。それまでろくな治療法がなかったんですよ。抗生剤もなければ抗癌剤も1950年60年代までほとんど何にもなかったような状態です。
一中 病気になったら諦めるしかなかったわけですよね。
津田 この半世紀ぐらいでようやっと使いものになるようになってきた。そんなもんだと思いますよ。
一中 それは重い発言ですね。
津田 いや本当。それをちょっと忘れている。音楽もそうだと思います。音楽はもっと短い。私が小さかった頃の日本の西洋音楽っていうのは、今から考えたら本当にオーケストラが下手でした。この10年ぐらいで世界のレベルになった。NHK交響楽団とかもすごくよい演奏になってきた。小さい頃はカラヤンとかバーンスタインの音楽が一流の音楽とされていた時代でしたね。
一中 まったく違う音でしたね。
津田 日本何をやってるのというぐらい、下手くそな感じでしたね。ヨーロッパの演奏能力も、バーンスタインとかカラヤンの頃よりもさらに上がってきています。ただ地域性が失われたと言っている人はいますけれども。ベルリンフィルもニューヨークフィルもウィーンフィルも同じような音になってしまった。
一中 指揮者をどんどん入れ替えてますからね。
津田 昔はオーケストラに男性しかいなかったですよ。100%男性でしたから。
一中 ウィーン生まれウィーン育ちでないとだめとかね。本当はそれを守ったほうがいいと思いますけれども。
津田 ただレベルは上がったと言われていますね。現在は、和洋両方のレベルの高いものにアクセスできるようになってきたというのが時代の特徴だと思います。だから今の若い人はたいへんですよね。身につけなければいけないものが我々の時代の倍ぐらいになっている。医学もそうだし、文化的なこともそうだと思います。世界中のことにアンテナを張り巡らせないといけない。今の若い人はそれで手が回らなくなって、昔の人が何をやっていたかを知らないでいろんなものを作って、一生懸命やっているんだけれども、それって30年前に流行ったやつじゃないみたいなことがときどき起こってますよね。
一中 昔の方は、昔のものを研究した上で初めて本当に新しいものができると考えていた。これ新しいだろうと思って、昔のものを研究していないでやったものは価値があるものにならない。
津田 残っていかないでしょうね。今ぱっと流行ったとしても。たいへんだと思います、今の若い世代の人は。本当に新しいものを作ろうとすることを、諦めているように思います。
一中 このごろ「YOASOBI」というユニットの女の子の歌い方をテレビで見たら、一中節がやっているように、1字ずつものすごく丁寧に繊細な神経を使いながら歌っていた。元々日本の歌にあったやり方で。それをやっている人が自然に出てきて、商業的なパワーをかけられていないのに、ネットでみんながそれを聞くようになっていることに、ある救いを感じるんですね。一中節ができた時代も、商業的なプロダクションがあって一中ってやつを売りだそうと思って、お金をかけて髪型も作ってやった訳じゃなくて、なんかこれはいいなっていうことで、はやったわけです。今はネットができたから、本当に上手な子、心ある歌を歌う子をみんながいいと思う時代になってきた。非常によい時代だと思います。
津田 伝統に新しい光が当たることになってくるわけですね。
一中 意外と捨てたもんじゃないかもしれない。
津田 この10年20年が勝負なんだと思いますね。息が絶えてしまうか、次に行くのか。残しまくらないといけない。下手すると消えてしまうものがいっぱいあって。特にこれから人口が減少して跡継ぎ問題が深刻になると、音楽に限らず漢方も後世に伝えられないかもしれません。そういう意味で今は非常に大事な時期なのかもしれませんね。かたや世界中にたいへんなニーズもある。新しいもの珍しいものを知りたい、見たいという。ここにつなげられると100年200年続きますけれども。ここで絶えてしまうと、もうわからなくなる。
一中 華佗の医学がずっと伝わっていたら、華岡青洲もあんなに苦労しなくてすんだわけですね。「残しまくらなければいけない」っていうのは、いいお話ですね。
津田 国家が予算を使って国家戦略としてやってもいいと思うんですよね。そうすると次の100年に知的財産権を主張できるわけです。国が大儲けできるかもしれないんです。間違いなく可能性があるはずなんですよね。
(終わり)
津田篤太郎(つだとくたろう)
1976年京都生まれ。京都大学医学部卒。北里大学大学院修了(専攻は東洋医学)。東京女子医大付属膠原病リウマチ痛風センター、JR東京総合病院、聖路加国際病院Immuno-Rheumatology Centerを経て、現在、NTT東日本関東病院リウマチ膠原病科部長。福島県立医科大学非常勤講師。著書に『未来の漢方』(森まゆみと共著、亜紀書房)『漢方水先案内 医学の東へ』(医学書院)『病名がつかない「からだの不調」とどうつき合うか 』(ポプラ新書)『ほの暗い永久から出でて 生と死を巡る対話』(上橋菜穂子との共著、文藝春秋)など。訳書に『閃めく経絡―現代医学のミステリーに鍼灸の“サイエンス”が挑む! 』(D.キーオン著、須田万勢らと共訳)がある。